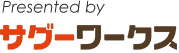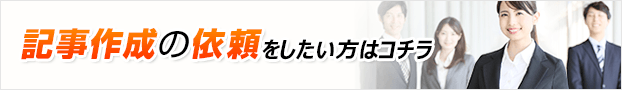【スキルアップ】ライティング上達のテクニックまとめ!!

文章を書いていて『上手に書けない』『うまく言葉が出てこない』と感じる人は少なくないのでは?逆にある程度書けるけど、もっと腕を上げたいと考えている人も多いでしょう。
文章は、ただ漫然と書いていても上手くはなりません。さまざまなテクニックを身に付けて、言葉を自由自在に使いこなすことが文章上達の「鍵」です。ここでは、文章上達に役立つテクニックの数々を紹介していきます。
この記事にはライティングをするにあたって押さえておきたいポイントが詰まっているので、たどり着いたあなたはラッキーですよ!
文章表現をブラッシュアップ!
ライティングするうえで大事なことは、相手に伝わる文章を書くということです。単に事実を書き並べるだけでは、読んでいて味気ない、退屈な文章になってしまいます。
さまざまなテクニックを駆使して、読んでいて楽しい、ためになる文章を書く必要があります。ここでは、良質な文章を書くための押さえるべきポイントをみていきましょう。
伝わる文章を書くにはコツが必要!
まず、どの読者層をターゲットにしているのかを決めてから書き始めるようにしましょう。
そして、文章の論点が明確であることが重要です。『結論を先に書く』と文章のブレが少なくなります。その際、文章は簡単で分かりやすい文章にするほうが好ましいです。難しい言葉はできるだけ簡単な言葉に置き換えましょう。もちろん、間違った用法や誤字脱字は論外です。
伝わる文章には句読点の使い方が大切!
文章を書く上で意外と見落としがちなのが句読点です。句読点のルールがでたらめな文章はとても読みにくく、内容が頭の中に入ってきません。読むうえでストレスを感じさせてしまうのも、句読点が正しく使われていない事が原因であることが多いのです。句読点は適切な箇所に入れるよう心がけましょう。
『てにをは』の正しい使い方も身に付けよう!
長めの文章になると、『てにをは』の使い分けがいい加減になることが少なくありません。『コーヒーが好きです』と『コーヒーも好きです』では、伝えたいニュアンスが違ってきます。たった一文字で文章全体が云わんとしている意味が変わってしまう恐れがあるのです。決して面倒くさがらずに、正確に『てにをは』を使うよう心がけましょう。
文節を意識したライティングも大事!
文節ごとに区切って文章をチェックすると、文章の違和感に気付きやすいというメリットがあります。『今朝は/頭痛が/ひどかったので/風邪だと/思ったので/学校を休みました』という文では、『ので』が重複して文章がくどくなっていることが分かります。文章の構造を意識すると、こうしたミスを見つけやすくなります。
段落への意識が読みやすさにつながる
通常、長い文章は段落によって分けられます。段落がなくても文章は成立しますが、長い文章を改行なしで延々と書くと内容が理解しづらくなってしまいます。適度な長さで段落を分けることで理解が容易になるのです。内容にもよりますが、300字~500字程度のまとまりで段落を構成するのが読者に対して親切かもしれません。
感嘆符『!』や疑問符『?』の使い方にも注意!
『!』『?』をどの位置に置くかで読み手に与える印象が変わってきます。つまり、位置を工夫することで、文章の見栄えをよくすることができるのです。『!』『?』を文章内にうまく盛り込むと、記事にリズム感が生まれ、読み心地をよくすることができます。逆に、使いすぎると下品になり、読んでいて不快な文章になりかねません。感嘆符と疑問符の使用はほどほどにしたほうがよいでしょう。
効果的な読点(、)の使い方で伝わり安さが変わる
読点の少ない平板な文章は、読んでいて印象に残りません。大切な部分が伝わりにくいのです。印象に残る読みやすい文章というのは、伝わりやすい文章でもあります。読点を効果的に使い、大切な部分を強調することで、読みやすく伝わりやすい文章を目指しましょう。
『かっこ』のルールってあるの?
『かっこ』についてですが、『かっこ』には、かぎかっこ・二重かぎかっこ・丸かっこ・角かっこ・波かっこ・山かっこ・隅付きかっこなど、いろいろな種類があります。実は、『かっこ』の使い方に厳密なルールはありません。ライティングの際、『かっこ』の使い方はクライアントの指示に従えばよいでしょう。
記事構成を考えよう!
読み手に文章を最後まで読ませるためには、しっかりとした文章構成が必要となってきます。起承転結を意識してキャッチーな導入文を考えるなど、記事全体の工夫が要求されます。文章を書く前に、まず全体の構成を考えることが重要です。
『序破急』で構成しよう
文章構成の概念の一つに『序破急』というものがあります。元は能の世界で使われていた言葉ですが、現在では、文章構成を指すようにもなっています。『序』は文章全体の概要を説明する導入部、『破』は中心となる物語、『急』は結論という構成です。起承転結と似ていますが、この『序破急』を意識しながらライティングすることで、自然な文章の書き方が養われます。
説得力を高めるには結論ファーストが重要!
読者を惹きつける記事をつくるためには、魅力的なタイトルと見出しが必要になってきます。そして、記事を構成するうえで大事なことは、いかに読者を最後まで惹きつけるかということです。
そのためには、先に文章の冒頭に結論を持ってくることがポイントです。読み手は欲しい情報をできるだけ早く手に入れたいと思っているからです。先に結論を書いたあと、その情報を補完する内容を盛り込んで、記事の説得力を高めます。
導入文とまとめが読み手を惹きつける鍵
導入文はどんな人をターゲットにしているのかを明確にする必要があります。次に、読み手に関心を持ってもらえるような問題提起をします。そして、それに対する解決案をこれから提示するという内容で本文に繋げます。まとめは、記事全体の結論を本文の内容を踏まえてしっかりと書く必要があります。導入文で読み手の関心を引き、まとめで記事全体の結論をつけるというイメージです。
『三段論法』と『起承転結』にもこだわりを!
三段論法とは、『大前提→小前提→結論』という3段構成で結論を導く論法です。前提のない文章から結論は生まれません。確固たる前提に基づいて導き出された結論は説得力があり、論理的な文章となりえます。
そして『起承転結』ですが、これは文章の基本です。『起承転結』のルールを守れていない文章は論理的になりません。起承転結の流れさえしっかりしていれば文章としてしっかり成立します。三段論法を活用しながら、起承転結をしっかり押さえた文章を心がけましょう。
ライティングテクニックを上げよう!
そつなく文章が書けるようになると、『もっと上手になりたい!』『もっと稼ぎたい!』と上を目指したくなるものです。そのために、新たなテクニックを身に付けるべく、さらなる努力をする必要があります。いくつかの上級テクニックを押さえていきましょう。
思わず目が止まってしまうようなタイトルを考えよう!
エンタメ系の記事では、わざと核心に触れないぼかした表現にします。逆に、必要な情報を探している人向けのハウツー記事は、具体的なタイトルをつけるほうが親切です。どちらの場合も中身が伴わないタイトルでは読み進めてもらえませんので、目を引くタイトルということに加えてコンテンツとのバランスも考えましょう。
単調な語尾の連続は違和感を与えてしまうことに
語尾が単調になるのを防ぐには、語尾のバリエーションを豊かにすることが基本です。体言止めや倒置法も文章のメリハリをつけ
るのに便利です。また、推定表現を文章中に加えることで、文章の流れを自然な感じにすることができます。
記事の掲載は何年にも渡ることを考えて!
『明日』『去年』といった時間表現は避けたほうがよいでしょう。時間の経過とともに記事の内容がズレる恐れがあるからです。同様に、『最近』などの表現も使用しない方が好ましいです。時間が経っても記事内容に違和感のない文章を書くことを目指しましょう。
見出しは読み手と検索エンジンの両方に効果が!
大見出し・中見出し・小見出しを作成することで、読み手に分かりやすい文章をつくることができます。また、Webの検索システムは見出しから記事を判断していると言われています。そのため、見出しに使うキーワードにこだわることで、検索エンジンに評価されるようになる可能性が高いです。
タイトルや小見出しのポイント
記事を完成させてからタイトルや小見出しを書くというテクニックを使うことにより、文章のテーマに沿ったものができやすくなります。タイトルや小見出しはインデックスの役割を果たすとされています。ですから、端的で簡潔かつインパクトのあるものを心がけましょう。
ライターに求められる語彙力
語彙力があれば、同じようなテーマの案件でも、それぞれに違う表現でライティングすることができます。語彙力を強化するためには読書が大切です。小説、ビジネス書、ノンフィクションなど、あらゆるジャンルの本を読むことで、ケースに応じて単語を使い分けられるようになることが期待できます。
間違えやすい表現に注意しよう!
文章を仕事とする人にとって、間違った文章表現は許されません。慣用句やことわざの意味をはき違えていたり、漢字の使い方を間違っていたりすると、読み手に伝えたい内容が正しく届きません。ここでは気を付けるべき文章表現についてみていきます。
『~たり』は誤用率が非常に高い表現です。
『本を読んだり、散歩をしたりしました』など、『~たり、~たり』と繰り返し使うのが正しい使い方です。ただし、『本を読んだりしました』だけの文章など、同類のことが他にもあることを暗示する文章では、副助詞的用法として『~たり』を単独で使用することがあります。文章に携わる仕事では、誤用表現には敏感になったほうがよいでしょう。
文章表現のタブーを知っておこう!
『必ず必要』などの二重表現は、ついやってしまいがちなタブーです。好ましくない表現なので避けるように注意しましょう。また『なので、』は、話し言葉では『ですので、』の意味で使用可能ですが、文章では、『なので、』を『ですので、』の意味で文章の書き出しに使わず『ですから』とします。また、三点リーダーの正しい使い方は意外と知られていないようです。『…』という具合に、一つだけ使用するのが無難です。
漢字の使い方にも、もっと注意を払いましょう。
同音異義語への注意はとても重要な部分です。漢字の変換候補に表示される同音異義語の意味の違いはしっかり確認しましょう。また、読みやすさを考慮した場合、難解な漢字はできるだけ避けたほうがいいでしょう。漢字とひらがなのバランスを考慮しながらライティングすることが大事です。
最終チェックでミスをなくそう!
記事を書き上げたら、必ず見直しをすることが大切です。ここで手を抜くと、あとから誤字脱字や違和感のある箇所が見つかって、結局書き直しという羽目になりがちです。ライティングするうえで、記事完成後の最終チェックは常識といってもいいでしょう。
Word(ワード)を有効に使いましょう
Word(ワード)の便利な機能を押さえておくことも、ライティング上達には欠かせません。文章を入力していると、赤や緑の波線が文字の下に出てくることがあります。赤い波線は明らかな入力ミスをチェックするものです。緑の波線は表現の統一にかかわる表記ゆれをチェックします。
また、文字カウント機能はライターにとって必須の機能です。『文章校正機能』と『文字カウント機能』はしっかり活用しましょう。
誤字脱字のセルフチェックが重要!
ライティングの基本ですが、誤字脱字のチェックは必ずしなければいけません。同じ言葉でも、漢字とひらがなの両方を使っているといった表記のゆれにも注意すべきです。同じ語尾や同じ表現を繰り返し使っていないかどうかも、単調な文章を避けるうえで重要です。
上質の文章を目指そう!
ライティングにはさまざまなテクニックが必要とされます。楽しくて読みやすい文章にするため、豊かな文章表現力が要求されます。冒頭から終わりまで読み手を飽きさせない構成を考える必要もあります。間違えやすい表現を避けて、漢字も正しく使用しなければなりません。
つまり、読み手にとって、楽しくて役に立つ文章を提供することがライティングの仕事なのです。『稼ぎたい!』『上手になりたい!』という人は、上質の文章を目指すべく、一つでも多くのテクニックを身に付けて努力を重ねましょう。
 この記事をシェアする
この記事をシェアする
みんなの感想文
はい・・・8人 / いいえ・・・2人
- 文章制作の基本を掲載しているという感じを受けました。初心者さんには重要な内容なので良いのかも…しかし、はっとするような内容の記事を求めていましたので、ちょっとパンチが足りないような気がしてしまいました。
- 基本の句読点や記号の使い方など、参考になる部分も多かったのですが、序盤の文章表現を「ブラッシュアップ」という表現に、少し身構えてしまいました。恥ずかしながらブラッシュアップの意味がわからないので、一度辞書で調べないと理解できず、すぐに頭に入ってきませんでした。私自身の知識不足のせいですが、英語よりもできるだけ万人に伝わりやすい日本語を用いたらもっといいかな?と思いました。
- この記事を読んで初めて「序破急」という言葉があることを知りました。「起承転結」よりも簡単で、すんなりと理解することができました。あと、結論を先に書くことも大切なのですね。これからは、この記事に書いてあったことを参考にしてライティングしたいと思います。
- コンテンツがとても充実していて句読点の使い方など、普段はあまり気にしないようなポイントも詳しく説明が出ていて、とても勉強になりました。各トピックごとに、より詳しい説明のあるリンクが添付されているなど読み応えも十分で、後の自分のライティングの参考にと、思わずお気に入りのページとして保存してしまったくらいです。
- 書き方のポータルサイト的記事です。文章のてにをはに始まってキャッチーな文章の書き方、誤用やタブー、ミスのチェック方法などライティング中に気になるものが網羅されていてそこから詳しい記事に飛ぶことができます。これは便利、と思いました。
- 言葉の使い方、例えば「なので」ではなく「ですから」と文章では書くというのは参考になりました。結論を先に書く、簡単な言葉で表すといったことから、初めて聞いた「三段論法」について知ることもでき興味深かったです。
- 普段ライティングの作業をしていて、うまく表現できなかったり、言葉が出てこないことがよくありました。相手に伝わる文章を書くためには、句読点や「てはには」など一見簡単に見えることが重要だとわかりました。文章の構造を意識して、相手にわかりやすくかけるようになりたいです。
- たくさんのテクニックが網羅されており、身につけなければなら無いと感じる事だらけでした。その中でも、すぐに実践しようと思ったのが、ワードを使っての文章校正機能です。自分では気づかないミスもこれを使えば確認できそうです。
- たくさんのテクニックを紹介してくれる大変為になる記事でした。私は特に序破急の構成を心がけるという部分が印象に残っておりこれまでまったく気にしていなかったので今後のライター作業において実践したいなと思いました。
- 大見出しと小見出しで読者を引きつけるテクニックは今まで気にしたことがなかったので、とても参考になりました。また三段論法といった手法は今の自分には難しそうですが魅力的で何とかマスターしたいなと思いました。